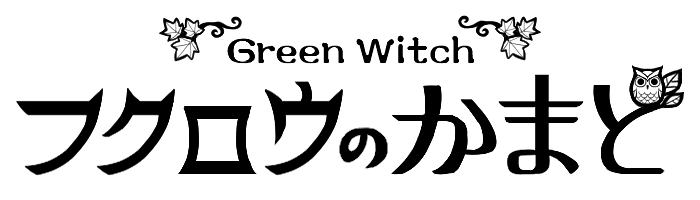『共感覚の魔女』に仕掛けられた文体の秘密!なぜ会話文から句点が消えるのか
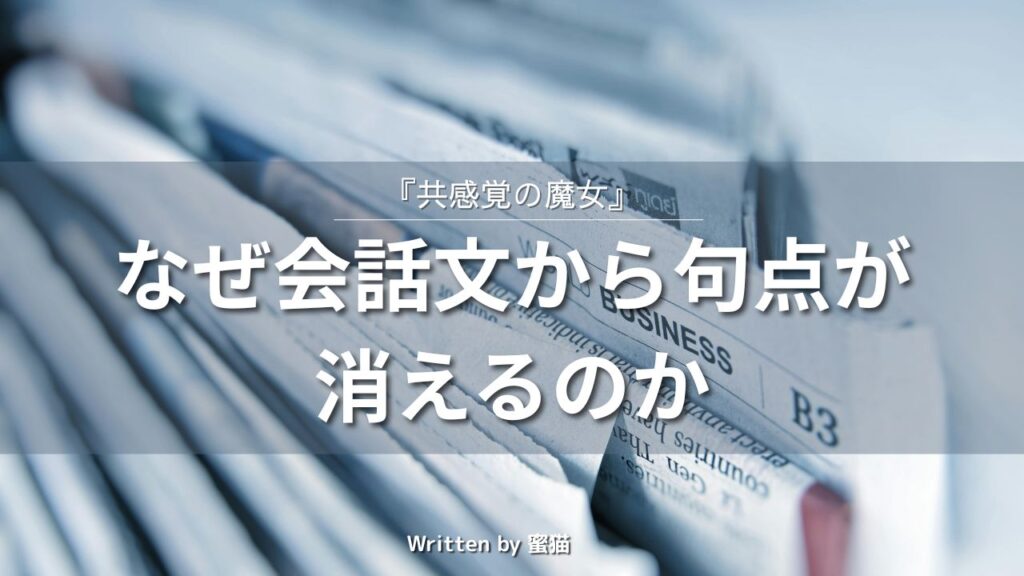
拙著『共感覚の魔女:カラフルな万華鏡を生きる』には、ひとつの仕掛けを忍ばせてある。
本作の序盤、子供時代のエピソードが語られる部分では、会話文を「~。」と句点つきで表記している。
しかし物語が進み、ある時点(p.165)を境にして、その句点がふっと消えるのだ。
以降は「~」とだけ閉じられ、句点のない会話文になる。
この変化は単なる文体の揺らぎではない。
作者であるわたしにとって、それは世界の見え方が変わった瞬間を示す符号である。
子供の頃のわたしは、ただ見えるものを見えたままに受け取るだけの存在だった。
だがある時を境に、外の世界の仕組みと自分の内側の感覚がかみ合い始めた。
その瞬間を境目として、文体から句点が消える仕掛けを施したのである。
つまり、この仕掛けは「わたしが現在を悟り、納得して生きるようになった瞬間」を象徴している。
お気づきの人はおられただろうか?
出版業界における「カギカッコ」のルール
出版業界では、会話文などでカギカッコ「」を使う際、閉じの直前に「。」を打たないのが基本らしい。
なぜなら、閉じカッコがすでに文の終わりを示しているため、句点を加えると二重表現になって冗長だからである。
新聞や雑誌、文庫本など多くの出版物では、このスタイルが広く採用されている。
特に新聞では、引用文や会話が多く登場するため、句点を省略することで字数を節約し、限られた紙面に効率的に情報を載せる工夫も行われている。
一方で、学校教育の現場では文末に「。」をつける訓練がされるため、教科書などではカギカッコの中でも句点をつけるスタイルが残っている。
文化庁の「くぎり符号の使ひ方〔句読法〕(案)」にもその名残がある。
つまり、学校教育の国語と、出版業界の現場ルールにはズレがあるというわけである。
まとめると、句点を入れないスタイルは、出版現場の「読みやすさ」や「効率」を重視する文化的慣習であり、決して文法的に誤りというわけではない。
反対に学校教育における句点の運用は、文末を明確にするための安全策として残っているという構図だ。
共感覚の子供時代と「理解されない悲壮感」
わたしの主観的な思いについては既に本書に書いたので、ここでは一般的に、共感覚者が子供時代にもつ苦しみを記しておきたい。
共感覚は、音に色が見える、文字に味を感じるなど、複数の感覚が結びついて現れる知覚現象である。
本人にとってはあまりにも当たり前の体験(それが普通!)であるが、多くの場合まわりの人には共有されない。
そのため、共感覚を持つ子供は「他の人も同じように感じているはずだ」と思い込み、初めて周囲から否定されたときに強い衝撃を受けることになる。
学校や家庭では、子供は自分の見えているものや感じていることを表現しようとする。
しかし大人や友人に「そんなのあるはずない」「気のせいだ」と言われてしまえば、子供は自分の感覚そのものを疑い始める。
これは単なるからかいではなく、自己存在の根本を否定されるような体験となりうる。
さらに、共感覚は検査や数値で簡単に証明できるものではない。
そのため「理解されない」状態が長く続きやすく、孤独感や悲壮感へとつながっていく。
心理学の研究でも、共感覚者の多くが幼少期に孤立や疎外を感じていたと報告されている。
つまり、共感覚者にとって子供時代は「感覚の豊かさ」と「理解されなさ」の二重構造にさらされる時期である。
このギャップは大きな苦しみを生み、やがて自己の表現方法や世界の見方に深い影響を与えていく。
魔女の掟との出会い
「魔女の掟(Wiccan Rede)」とは、ウィッカの復興異教主義(ネオペイガニズム)宗教やウィッチクラフトに基づく大切な行動規範を、詩形式にした声明である。
長文なので、簡潔に要点をまとめると以下の三点である。
- 何物も害さない限り、あなたの望むところを成せ
- いいことも悪いことも、三倍になって自分へ返る
- 世界でいちばん尊いものは「愛」である
(『共感覚の魔女』p.316より引用)
この思想は、世界を畏れとともに理解し、調和の中で生きようとする態度を支えている。
共感覚者にとって、日常はすでに複雑な感覚の網目で成り立っている。
幼い頃はその複雑さをただ抱え込むしかなく、周囲の理解も得られずに苦しむことが多い。
しかしこの教えに触れることで、「自分の感覚が間違っているわけではなく、自然の理の一部なのだ」と気づくことができる。
この気づきは、生きづらさを軽くする。
世界は敵対するものではなく、因果の流れに沿えば自分も自然に溶け込めるのだという確信が得られるからである。
すなわち、共感覚という個別の特性が、魔女の掟によって「生きるための感覚」として肯定されるのである。
よりよく、ラクに生きるために
魔女の掟の思想がもたらすのは、複雑な世界を「流れ」として捉える視点である。
自然の摂理に逆らえば軋みが生まれ、流れに沿えば無理なく物事が進む。
これは単なる信仰ではなく、因果律を日常生活の中に引き寄せて理解する方法でもある。
この視点を持つと、過去や未来にとらわれて自分を責めたり、先の見えない不安に押しつぶされたりする必要がなくなる。
重要なのは「今ここでどう行動するか」であり、その選択がめぐりめぐって自分に返ってくることを知っているからだ。
共感覚者にとって、ときに世界はあまりにも刺激に満ちていて、過剰に感じられることがある。
その中で「流れに逆らわない」というシンプルな指針は、日々の生き方をラクにする。
努力や我慢でねじ伏せるのではなく、自然の調和の中に身を置くことで、自分も世界も少しずつ丸く収まっていくのだ。
文体が物語る「丸くなる」こと
本書の中で、会話文から句点が消える仕掛けを入れたのは偶然ではない。
子供時代を象徴する「~。」という書き方は、視野が直線的で、目の前のものしか見えなかった頃のあり方を映している。
そして句点がなくなり、出版業界のルールに沿った文体に移行することで、視点は広がり、世界を円環的に捉えられるようになったことを示している。
カギカッコの末尾に句点をつけないというルールは、紙面上の省略や読みやすさのために存在する。
しかしここでは、その規則性を文体上の変化として利用し、「悟り」と「成長」の象徴とした。
冗長を削ぎ落とし、すっきりとした形に整うこと。
それは、世界の仕組みに自分の感覚が調和した瞬間を表現するのにふさわしいと思えたからだ。
つまり、『共感覚の魔女』における文体の変化は、単なる技法ではなく、子供から大人へと移行していく過程そのものを物語っている。
角ばった「。」から、丸く収まる調和の「」へ。
その流れを辿ることが、本書のもうひとつの読後体験なのだ。
感謝
本書のp.6にも記した通り、
「編集部注・本書における色彩の表現方法、会話文における句点の有無など、すべての表記には著者の五感をありのままに書き表す趣向が凝らされています」
という一文が添えられている。
実はこの一文の裏には、わたしからの少し奇妙なオーダーがある。
「(p.165)以降から閉じカッコ前の句点が消えます」という特殊な仕様だ。
通常の校閲基準では想定されないお願いだったが、編集部の皆さん、担当編集者、そして外部で原稿を丹念にチェックしてくださった校正者の方々が、最後まで根気よく寄り添ってくださった。
ここに、心からの感謝を記したい。
この本が読者の手に届いたのは、わたし一人の力ではなく、多くの人々の支えがあってこそ実現したものである。